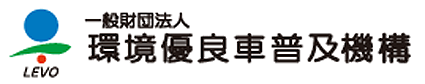令和6年度補正予算 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
令和6年度補正予算 その他Q&A
- 車両に関するO&A
- 充電設備に関するQ&A
- その他Q&A
- 全体版Q&A
☎お問い合わせ先✉
🚚車両担当🚚
☎:03-5944-0883
(平日9:00~12:00/13:00~17:00)
✉:evhojo*levo.or.jp ←「*」を「@」へ変更してください
⚡充電設備担当⚡
☎:03-5341-4728
(平日9:00~12:00/13:00~17:00)
✉:juhojo*levo.or.jp ←「*」を「@」へ変更してください
その他Q&A
申請後に会社の組織再編が予定されているが、補助金申請に当たって気をつける点はあるか
▶財産処分について、一部運用が変更されておりますので、申請前に事前に御相談ください
一体的導入とはどいうことですか
▶商用トラックの導入者(補助申請者)が車両を置く敷地(事業所、営業拠点)等にその車両を充電するために設置する充電設備を一体的に導入することです
(なお、補助申請者等で車両の導入者と充電設備の導入者が別の場合は一体的である旨の契約書等が明確にされた導入のことです
補助対象事業者に記載のある「その他環境大臣の承認を得て、機構が適当と認める者」とは具体的にどのような者ですか
▶具体的には機構にご相談ください
交付決定後、申請の内容変更(車種、充電器の変更など)がある場合、届出の様式はありますか
▶補助金の額の変更申請を行う場合は交付規程の様式第2(第6条関係)にて変更交付申請を行ってください。但し、台数減の場合は様式第2の変更交付申請ですが、台数増分については新たな交付申請を行ってください
審査結果については審査終了後に応募申請者宛てに通知するとしていますが、通知方法は何で行うのですか
▶システム申請、電子メール申請、紙による申請の場合を含めて、基本的には電子メールにて「交付決定通知書」を添付して通知いたします
受付期間(令和8年1月30日)より前に予算執行額に達したらどうなるのですか。早めに申請したほうが有利ですか
▶受付順に審査し、予算の残額が2割程度になりましたら、それ以降の交付申請については、受付順による審査を行うことはせず、当該日付から令和8年1月30日までに申し込みのあったすべての交付申請を対象に審査を行います
また、予算残額を超える申請があった場合には、初めて申請を行う事業者や脱炭素先行地域に選定された地域内の事業所等に導入する事業者を優先して抽選するなど配慮したうえ補助対象事業者を決定します
交付申請から交付決定までにどのくらいの期間が必要ですか
▶申請後に機構で書類内容を確認し、不備不足なく受付した日から30営業日以内に交付決定を行い「交付決定通知書」を発行いたします。なお、審査に時間を要するもの、申請が集中した場合はこの限りではありません
交付申請時の完了予定日が伸びる場合、手続きが必要ですか
▶特段の手続きは必要はありません。ただし各年度にて定められた完了実績報告書の提出期限を超えないことに併せ完了実績報告書、精算払請求書の審査期間が必要なことから余裕のある行程が必要です
申請を行いましたが、都合により申請を取り下げることはできますか。次に申請する際にペナルティなどありますか
▶可能です。対象の申請番号等をご用意の上、機構にご連絡ください。交付決定前ですと「取下げについて(届出)」また、交付決定以降の場合は「中止(廃止)承認申請書」を提出してください。取り止めによるペナルティはありません
予算の消化状況は公表されるのですか
▶機構のホームページに定期的に予算執行残高を掲示していく予定です
補助対象となる車両、充電設備の名称、型式等を教えてください
▶機構のホームページにて確認できます。
車両 :https://www.levo.or.jp/subsidy/hoseiyosan-6/truck-6/
充電設備:https://www.levo.or.jp/subsidy/hoseiyosan-6/jyuuden-6/
いわゆる割賦購入の場合でも申請できますか
▶割賦購入では申請できません
地方公共団体の他の補助金と併用する場合、申請できますか
▶申請できます。原則的に国の補助金に相当する地方公共団体の補助金の額を記入してください
補助金に相当する額が総額の場合は、内訳を記入してください。リース料金の総額が地方公共団体の補助金と合算されている場合のリース契約については、国分と自治体分の内訳を記入するとともに月々のリース料金で国の補助金に相当する額が必ず還元されている事実が分かるように記載して下さい
自家用のEVトラックや充電設備についても申請できますか
▶車両総重量 2.5 トン超のEVトラックを自家用(レンタカーを含む。)として使用する場合、交付申請を行うことができます
(車両総重量 2.5 トン以下の自家用トラックについては、申請はできません。)
申請者になるにはどのような要件がありますか
▶① 貨物自動車運送事業者
② 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量 2.5トン超の車両に限る。)
③ 商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者(①、②、④、⑦に貸渡しする者に限る。)
④ 地方公共団体
⑤ 貨物自動車運送事業の分社等により、自らが50 %を超える出資比率によって設立した子会社たる貨物自動車運送事業者に、自らが所有するトラック車両を貸与する者
⑥ トラックと一体的に導入される充電設備を所有する(リースの貸渡し先を含む)者(①、②、③、④、⑦のトラック車両と一体的に導入される場合に限る。)
⑦ その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て、機構が適当と認める者
申請できる者は、自動車検査証に記載された所有者または使用者ですか
▶車両は補助対象車両の自動車検査証上の「所有者」です、充電設備は、補助対象車両の自動車検査証上の「所有者」及びトラックと一体的に導入される充電設備を所有する事業者です
車両、充電設備について、購入・リースのいずれも認められますか
▶購入・リースのいずれも認められます。ただし、割賦購入は認められません
申請総額が予算額を超えた場合、一申請あたりの補助額が減額されますか
▶令和6年度補正においては、補助額の減額はありません。複数年度事業で申請した場合で、翌年度の補助事業は、政府において次年度に所要の予算措置が講じられた場合にのみ行いうるものであり、次年度の見込み額に比較して大幅な予算額の変更や予算内容の変更等が生じたときは、補助額や事業内容の変更等を求めることがあります
リース会社と運送事業者が割賦契約を行い、所有者はリース会社で、ディーラーに代金支払済みの場合は、申請できますか
▶申請できません。リースによる導入の場合、補助の対象はあくまでリース会社と運送事業者とのリース契約によるもので、割賦形態(売買契約)は申請できません
リース契約を締結する場合、例えば、「リース料金が月毎に変動するような形態」の契約は認められますか
▶リース契約の中に補助金支給分が減額されていれば、リース金額が変動するリース契約も認められます。リース料金算定根拠明細書に内容を明記してください
リースの場合、リース会社は交付を受けた補助金をそのまま使用者の運送事業者に一括で支払っても良いですか
▶リースの場合、あくまでもリース契約に則った月額リース料金に補助金を反映させることとしていますので一括で補助金を支払うことについては認められません
契約書、リース料金算定根拠明細書の作成の際に留意してください
転リース取引は当該補助の対象ですか
▶対象です。ただし、共同事業者申請書、中間会社の契約書の写し、算定根拠明細書等転リース取引の取引関係を証する書類が必要です
なお、リース契約書の約定に転貸リースを認める旨の文言がない場合には、三者間の覚書等の合意締結文章のコピーの提出が必要です
地方公共団体の補助事業との併用はできますか。また、協調補助は必要ですか
▶地方公共団体の補助との併用はその補助金が国の国庫補助を原資としていなければ可能です。なお、併用に当たっては、その補助事業の執行団体(自治体等)に確認してください。また、地方公共団体等のいわゆる協調補助は不要です
法定耐用年数の期間内に会社の社名変更等により使用者名が変更になった場合どうすればよいですか
▶社名変更等による使用者名の変更であることが、登記簿謄本等で確認することが可能な場合、補助金の返還手続きはありません。ただし、合併や事業統合により所有者(リースの場合使用者)が別法人になる場合(申請時点で使用者の変更の詳細(いつ、どこの、誰に)が確定している場合は除き)は財産処分に該当することがありますので、事前に必ず機構への届出が必要です。なお、機構の承認を得ずに処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全額返納が必要な場合もあります
リースを利用の場合、事業を継続できなくなった場合に補助金の返還は生じますか
▶財産処分制限期間内に補助事業の全部又は一部を継続することができなくなった場合、補助金の全部又は一部の返還が生じます。事前に必ず機構への届出が必要です
補助金受領後に申請内容と変更等が生じた場合、届け出は必要ですか
▶変更の内容によって、軽微な届出以外で国への承認手続き(補助金の返還等)が発生する場合もあるため、事前に届出してください
リースの場合で補助金の返還にあたる事由が生じた場合、補助金を返還するのはリース会社ですか、使用者ですか
▶車両等の財産を保有する代表申請者であるリース会社です
圧縮記帳は適用されますか
▶補助事業者が法人の場合、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入(圧縮記帳)の規定(法人税法第42条)の適用を受けることができます。規定の適用を受ける場合は、一定の手続きが必要となるので、所轄の税務署等にご相談ください
国の負担金又は他の補助金と併用することは可能ですか
▶本事業の補助事業により導入する設備等については、補助対象事業の基本的要件に適合するものとして、国からの他の負担又は補助金(負担金、利子補給金等を含む。)を受けていないことを必要要件としていますので、併用はできません
一方で地方公共団体等からの負担又は補助金を併用する場合には、当該補助事業が地方公共団体等の実施する事業等で併用できる制度になっている必要があります。そのため地方公共団体等の負担又は補助金と併用が可能な場合は、申請の際、地方公共団体等の実施する事業に係る負担又は補助金を可とすることが分かる交付要綱等の写しを提出してください
交付申請書に補助対象車両、補助対象充電設備の申請番号を記載する項目があるが何を記載すればよいですか本事業により導入する設備等は国からの負担又は他の補助金を受けてはならないという条件があるが、過去に補助金を受けていた場合も該当しますか
▶過去の負担又は補助金は該当しません
ファイナンスリース取引とは、どのようなリース取引ですか
▶リース取引を途中で解約できず(ノンキャンセラブル)、また、リース資産に係るコストをすべて負担する義務(フルペイアウト)を負うリース取引のことです
ファイナンスリースを活用する場合の注意事項は何ですか
▶ファイナンスリースを活用する場合については、「補助金を受けない場合のリース料」から「補助金を受けた場合のリース料」を差し引いて補助金相当分が減額されていること、法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用することが契約内容に含まれていることが必要です
補助金はいつ頃入金されますか
▶補助事業者の補助事業が完了し、完了実績報告書(精算払請求書)を提出し、機構からの交付額確定通知書の通知を受けた後、機構から補助金を振り込みます
申請書類に不備(整合性がない・書類不足等)がある場合、何の連絡もなく申請は却下されますか
▶申請書類を受付後、申請書類を精査し、申請書類に不足がある場合等については、機構から連絡いたします
電子メール申請の際に機構へ「識別番号の依頼を行う」とあるが、これは何の番号ですか
▶初めての申請者は、申請の前に機構あてにメールで「識別番号」の付与依頼を行います。これは申請する際に申請責任者を明確にするとともに代表者印を省略を可とするものです。交付申請する際は機構から附番された5桁の「識別番号」を記載のうえ、申請してください
※機構の他の補助事業で「識別番号」を取得済の場合は、その番号をご使用ください
「識別番号」で依頼した時の担当者の異動やメールアドレスに変更が生じた場合、何か手続きは必要ですか
▶責任者・担当者、メールアドレス等記載内容に変更がある場合は、機構から送付した識別番号通知に変更部位を朱書き修正して送付してください。
※なお、登録された「識別番号」のメールアドレス以外から届いた交付申請書は受理できません
交付決定通知書に「申請番号」とあるが、これは何の番号ですか
▶機構で申請書の受理後に「25」から始まる6桁の「申請番号」を附番し送付します。以後の申請、報告等の手続きについては「申請番号」を記載してください
交付額確定通知書に「LEVO管理番号」とあるが、これは何の番号ですか
▶機構で完了実績報告書を受理、審査後に額の確定を行う際にトラックは車両毎、充電設備は機器毎に「LEVO管理番号」を附番します
車両はリースで購入し(所有者:リース会社)申請、充電設備は運送会社(使用者:運送会社)で申請はできますか
▶申請できます
昨年度は申請の際に営業所名を記載する必要があったが、改正を行ったのですか
▶申請時に1事業者あたりで車両数、充電設備設置台数(口数)が決定していれば申請はできますが、営業所名、使用の本拠の位置が決定している場合は原則的に記載してください
ただし、完了実績報告書の提出までに営業所の決定は必要(車両数≧充電口数))です
申請者(車両の所有者)は変わらないが、使用者が法定耐用年数期間の途中で変わることが確定している場合、申請は可能ですか
▶申請時点で使用者の変更の詳細(いつ、どこの、誰に)が確定している場合は、その根拠資料(契約書等)を示して共同で申請することは可能です。ただし、申請時点で詳細が確定しておらず、申請後に使用者の変更が発生した場合や申請時と異なる変更がなされた場合は、これまでどおり財産処分の対象です
トラックと充電設備で補助事業の完了予定日が異なる場合交付申請はどうしたらよいですか
▶完了予定日が異なる場合でも通常通り同時期又は別々に申請を行ってください。車両・充電設備の申請時には一体的導入となる車両もしくは充電設備の申請番号を記入してください
交付申請書に補助対象車両、補助対象充電設備の申請番号を記載する項目があるが何を記載すればよいですか
▶車両、充電設備のどちらか最初に申請した際に申請番号を付与しますので、次の申請では付与した番号を記載してください
交付申請時にすべての書類が揃わなくても申請してよいですか。後日、追加資料の提出は可能ですか
▶申請に必要な書類が無いと受付ができません。申請時に必要な資料が揃った段階で申請してください
申請窓口はどこですか
▶一般財団法人環境優良車普及機構「商用車等の電動化促進事業」補助事業執行部が窓口です。電子申請メールアドレスは「tjdenshi@levo.or.jp」(車両・充電設備共通)です
申請書は電子メールで行うのですか
▶原則電子申請(電子メール、jGrants)です
電子メール申請では、申請者確認用「識別番号」を発行させていただきます。 初回申請前に必ず識別番号発行依頼書にてevhojo@levo.or.jpへご連絡下さい。以降、交付申請時等に使用してください
jGrants 申請では、申請書類を PDF 化して(データシートはExcel のまま)、アップロードしてください
電子申請の環境のない場合には、郵送により申請を行うことができます。(その場合は代表者印が必要です)
共同実施を行う際、代表事業者は誰にすればよいか
▶代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産の全部又は一部を取得する者に限るものとしており、この要件を満たす方が代表事業者です
なお、ファイナンスリースを利用する場合は、ファイナンスリース事業者が代表事業者です
申請書の「責任者」欄は誰にすればよいですか
▶会社等の組織において、補助事業に関わる業務を実際に行う部署の責任者(部長等)としてください
申請書の「担当者」欄は誰にすればよいですか
▶補助事業に関わる業務を実際に行い、機構と連絡を取り合える方としてください
なお、窓口となる方の所在地(書類を受領する住所)を記入してください
消費税は補助対象ですか
▶消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税」という。)は、補助対象経費から除外して補助金額を算定してください。ただし、以下の補助事業者については、消費税を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします
①消費税法における納税義務者とならない補助事業者
②免税事業者である補助事業者
③消費税簡易課税制度を選択している(簡易課税事業者である)補助事業者
④特別会計を設けて補助事業を行う地方公共団体(特定収入割合が5%を超える場合)及び消費税法別表第3に掲げる法人の補助事業者
⑤地方公共団体の一般会計である補助事業者